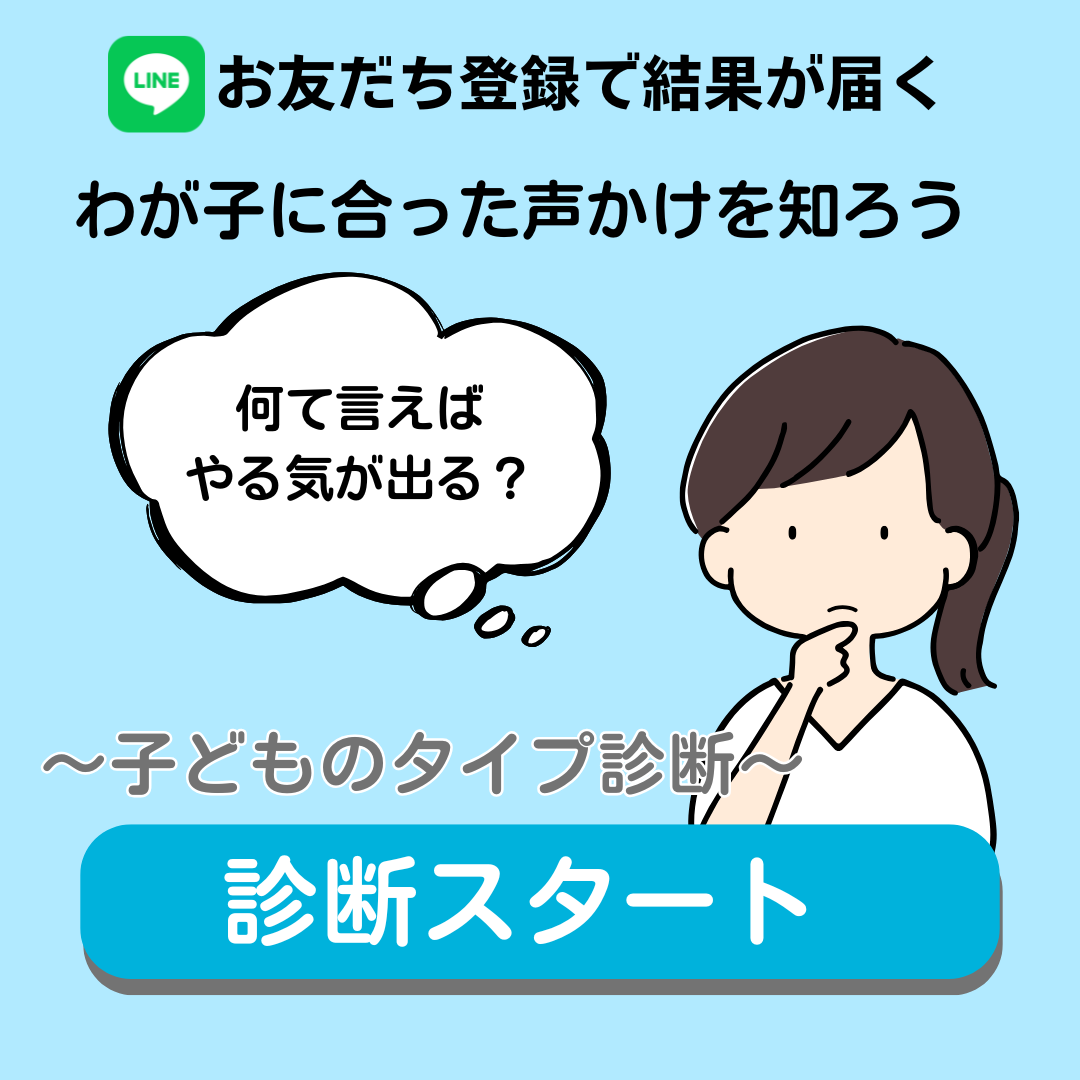こころ
女だからってなめるな!未来のなでしこを育む負けん気のつくり方
公開:2015年12月16日 更新:2021年1月27日
■サッカーが楽しいからがんばれるし、自分で考える習慣がつく
「サッカーで技術はもちろん大切ですが、私は小学生年代の子どもたちであれば、サッカーを楽しいと思える心を育てることが重要だと考えています。サッカーが楽しいから、またやりたい、次の試合に勝つためにどうすればいいのだろう、と主体性を持って考えることにつながるからです」
「またやりたい」と思うことで、サッカーをプレーする時間が増え技術も上達します。逆に、やりたくないと思っている子を誘っていくら練習を重ねてもなかなか上達しません。実際、小林さんはどのように子どもたちと接しているのでしょう。
「今はまだプレーヤーとして動けるので、教えるというよりも一緒にプレーしてサッカーの楽しさを伝えられるように心がけています。サッカーというスポーツには、ひとつしかボールがないので、幼児や小学校低学年の子どもたちの中には、積極的にボールを追いかけてずっと触っている子もいれば、どちらかというと消極的でなかなかボールに触れない子もいる。ボールに触れない子は、サッカーの楽しみ方がわからないのだと思います。そういった子に、ゴール前でパスを出してあげる。その子がそのボールをゴールに蹴りこんだら、一緒に喜んであげる。私と一緒にプレーすることで、サッカーを楽しいと感じてくれる子が一人でも増えてくれたら本当に嬉しいです」
やんちゃでボールによく関わる子は、負けず嫌いな傾向にあるため、あえて点を取らせないようにすると、悔しがってどうすればゴールできるかを考えるようになり、結果的にサッカーが上達すると言います。
「私たち大人が、"子どもはこうだ!""サッカーはこうだ!"と決めつけるのではなく、子どもそれぞれに合った関わりかたを探し出していくことのほうが重要だと思っています。私が子どものころ、周囲の大人たちがそうしてくれたことで成長できたと実感しています」
小林さんが小学生のころ、少し遠くまで試合に行くときには、試合後に家族でごはんを食べに行くことが多かったそうです。
「試合後においしいものを食べて、プレーを褒めてもらう。そうすると、次もがんばろうと思えました。お父さんには、私のプレーについて"ダメだったところはあまりいわないで!"と思っていました。そうすると、お父さんもそれを感じ取ってその日にはいわず、次の試合の前に話してくれるようにしてくれました。そういう親の気持ちって子どもも感じ取るものですよね」